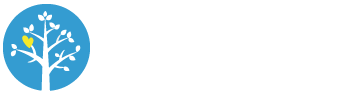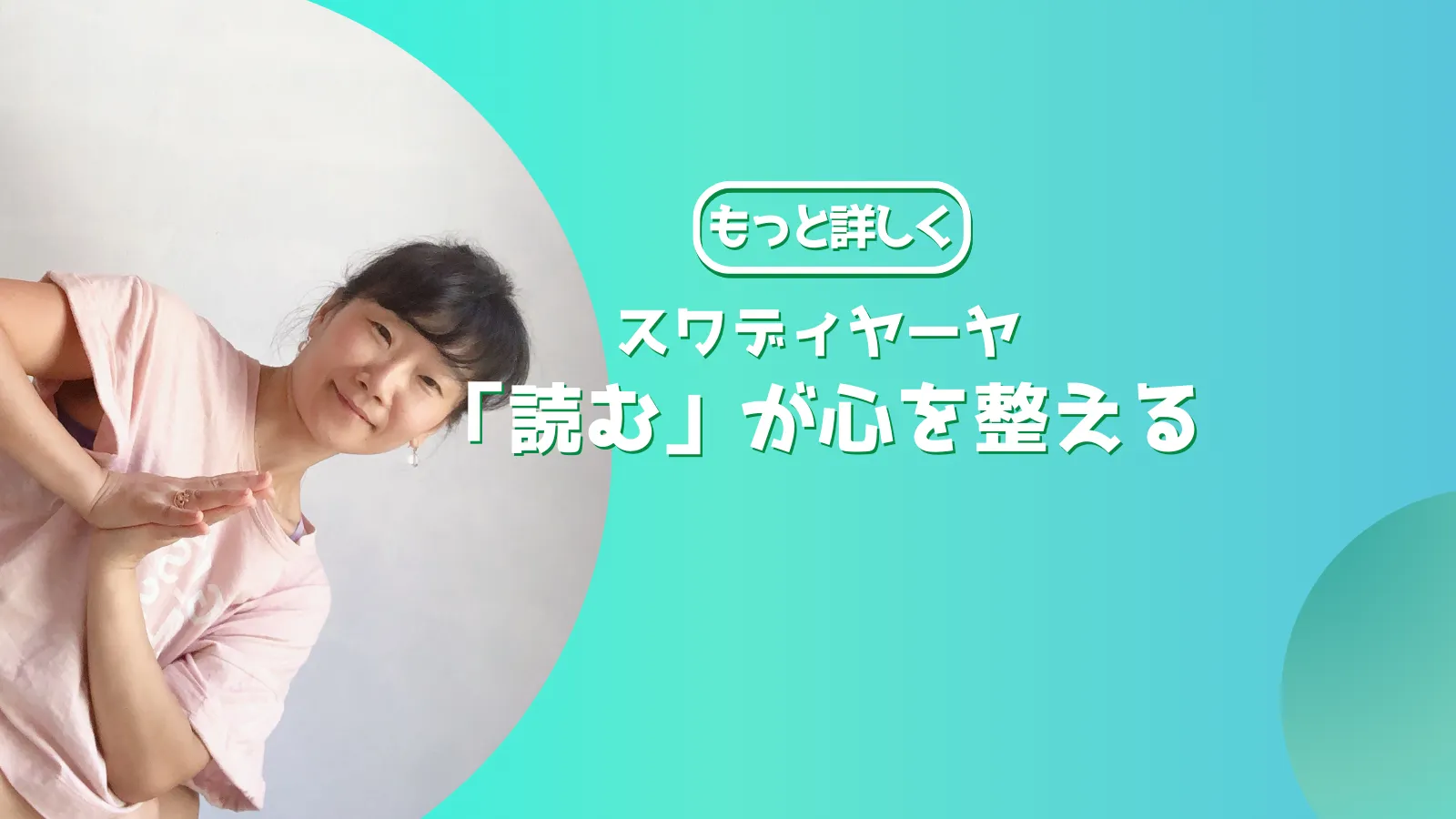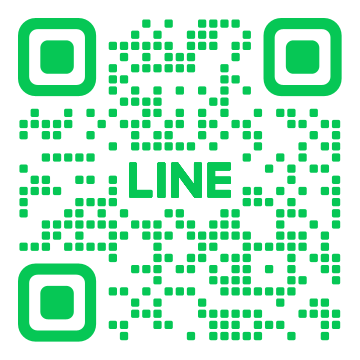この記事の本文中には、紹介している本への広告リンクが含まれています。
「ヤマ・ニヤマを日常に」シリーズ――スワディヤーヤの学び
これまでの記事で、ヤマ・ニヤマの中からアヒムサ(非暴力)を「花の福袋」を通して、タパス(精進・自己鍛錬)を「新月と新年のエネルギー」を通して考えてきました。(各記事へのリンクは記事末尾にて)
ヨガの教えは、決して古くて難しいものではなく、日常の中にふと現れる気づきを通して体験できるものです。それを知っていただきたいなと思いながらこのシリーズを続けています。
今日は、ニヤマの一つである「スワディヤーヤ(学習・読誦/聖典の学び)」 についてお話しします。
スワディヤーヤとは?ヨガの八支則における学びの実践
スワディヤーヤの意味と重要性
スワディヤーヤを簡単に言ってしまうと「本を読みましょう」なんですが、それだけではありません。大切なのは、それを通じて「自分を知ること」ができるかどうか、です。
日々の経験をどう学びに変えていくのか、その学びを通じて自分自身とどのように向き合うのか――そんなことを考えながら、ワタシが今、手元に置いている本たちについてもお話ししていきます。
アシュタンガヨガ(ヨガの八支則)のニヤマに含まれるスワディヤーヤ。
日本語にでは「学習」とか「読誦/聖典の学び」などと訳されますが、ワタシの感覚では「いい本を手元に置いて読むこと」に近いかもしれません。
今の時代は調べたいことや学びたいことがあればインターネットをちょっと活用するだけで、無料で手軽に最高レベルの講義を自分の好きな時間に受けることもできます。それは本当にいい時代だなーと思います。
でも、その受けた情報をどれだけ自分のものにできているか?
知識が増えても日常生活でちゃんと活用できるかというと、なかなか難しいのではないかと思います。時には、逆に、その情報を中途半端に見聞きしたが故に応用する段階(実生活)で間違って活用してしまうこともあるのではないでしょうか。
まぁそれも学びの過程の一つなので、他人がとやかく言うものではありませんが。
この記事を見つけて読んで下っているあなたには、できるだけ遠まわりせずに、より深い学びに繋がる読書のヒントをお伝えしたいと思っています。
学びのための読書が「自分を知る」ことにつながる
なぜ「自分を知る」ことが重要なのか?
ここでいう学びとは、ヨガ実践の目的の一つである「自分を知ること」にあります。
少しだけおさらいになりますが、どうして自分を知ることが大切なのでしょうか。
想像してみましょう。
まったくよく分からない人と一緒の時って、なんとなく緊張しませんか?相手が何を考えているのかがわからずに、次に何が起こるのかも見当がつかない。だから無意識に警戒し、心も落ち着かなくなります。
実はそれと同じことが自分自身にもいえるのです。自分を知らないということは、一番身近にいる人がどういう人なのか分からないまま過ごすってことですよね。
まず自分を知ることが、自分が自分の内側でリラックスするために必須条件なのです。
読書と瞑想の関係
自分を知るために五感をまず取り戻しましょうというのはもうお分かりですよね。
それが詳しく書かれているのがワタシの本です(『感じるヨガで、』)。
少し話が逸れてしまいました。(笑)
自分を知るのに瞑想はとても有効ですが、もう一つ大きな手助けとなるのが、読書です。
他からの刺激(情報)を受けることでその刺激が自分の中にどう波紋を作っていくのか、新しい何かが生まれるのかを観察する。
それがスワディヤーヤの本質でもあります。
ワタシが手元に置いている本たち
ワタシの本棚には、ここ10年ほど、ずっとそばに置いている本が何冊かあります。時期によって入れ替わることもありますが、長く大切にしているものは変わりません。
同じ本でも、数年前読んだ時と今読んだ時では全然違うメッセージを受け取ることがほとんどです。過去にはただの知識として理解していたことが、このタイミングで腑に落ちる感覚があったり、点が線として繋がったり、それが面となって自分の内側にすでに層になっていたなんてことに気づけたりします。
また、すでに自分の中に根付いている考え方でもうまく言語化できないこともたくさんあります。そんな時本の中で「まさにこれ!」というこういう表現に出会うと、自分の中の引き出しが増えていき、学びがより深まります。
それでは、ワタシの手元に置いてある本をいくつかご紹介していきましょう。
禅マインド ビギナーズ・マインド 鈴木俊隆
この本『禅マインド ビギナーズ・マインド』は、アメリカで禅を広めた鈴木俊隆老師が、アメリカ人向けに語った禅の講話をまとめたもの。スティーブ・ジョブズが愛読していた本としても知られています。
ワタシがこの本に出会ったのはアメリカに滞在していた時。友人の本棚に英語版があり、パラパラとめくってみたらなんとなくわかりやすいかもという印象でした。早速日本に帰ってきて日本語バージョンを購入しました。
東洋的思想のベースが全くないアメリカ人向け初心者に語られる内容は、日本人ならなんとなく持っている仏教的ベースがあることでほとんどの方は簡単に理解できると思います。
でもここが落とし穴で。(笑)
「わかっているけど全然できてないよね」と現実を目の前に突きつけられる感覚があるのではないかなーと思います。
そういう意味で手元に置いて、そうだそうだコレ忘れてたなーと自分の生活を省みるのに重宝しています。
ヨーガといのちの科学 スワミ・チダナンダ講演 小山芙美子編
こちらの『ヨーガといのちの科学 スワミ・チダナンダ講演』は結構ガチなヨガ本ですが、初心者の方にもシームレスにヨガ哲学や独特なヨガ単語が理解できるような語り口で構成されています。
日常生活の延長線上にヨガの学びがあるということや、耳慣れないヨガ独特の言葉の概念などがさらりと解説されていて、その概念を少し理解するだけでも、今の自分の思考をうまく整理することができるのではないかと思います。
ワタシも基本に戻ることや、どこに向かっているのかを再確認したりするなどに役立てています。
読誦(音読)のすすめ
またスワディヤーヤは「読むこと」だけではなく「読誦すること」も含まれているということを少し強調しておきたいなと思います。
「音読」のすすめ
これは好きだな、と思う文章をお部屋の空間に向かって読んでみましょう。その空間の空気が、その読む声で震えるのを自分が浴びるということです。
なので、あまり家具や物がないお部屋でやるとより効果が実感できます。自分の声であっても、自分の好きな言葉のエネルギーで覆われる、満たされる体験ができるはずです。
その本の内容が前述した学びの本であれば、その内容が内側と外側から自分に浸透していきます。
黙読とはまた違った感じで自己化されていきます。
以前、体験会も開催しました
去年か一昨年かな、ワタシが好きな小説ポールギャリコの「雪のひとひら」を音読するのを聞いていただくZOOMミーティングを1回開催しました。
これは、小説というジャンルのものではありますが、女性の生き方の一つの指南書のように思っているので何度も読み直している本です。なので、その時はこんなことはお話ししていませんでしたが、実はワタシのスワディヤーヤのお福分け(お裾分け)のつもりでしたということです。
今度、自分のお気に入りの本を持ち寄るミーティングなんかも開いたら面白そうかも?
あなたもスワディヤーヤをやってみて
いずれにしろ、自分の軸や核となるものを補完してくれるような本に出会えている方は、それでもうすでにスワディヤーヤの準備が整っているっていうことです。
まだの方は、好きな本を見つけるようにアンテナ張ってみましょう。
もうすでに見つけている方は、日々の糧にそれを活用してみましょう。
学びに終わりはありません。
「ヤマ・ニヤマを日常に」シリーズ
今後も少しずつ順番に書いていきますね。乞うご期待!
【ヤマ(社会的な倫理規範)】
アヒムサ(非暴力)☜ https://kaonyoga.com/inner-soul-yoga-ahimsa/
サティヤ(正直)☜https://kaonyoga.com/inner-soul-yoga-satya/
アステヤ(不盗)
ブラフマチャリヤ(禁欲・調和)
アパリグラハ(不貪・執着しない)
【ニヤマ(自己鍛錬・内的規律)】
シャウチャ(清浄)
サントーシャ(知足)☜https://kaonyoga.com/inner-soul-yoga-santhosha/
タパス(精進・自己鍛錬)☜ https://kaonyoga.com/inner-soul-yoga-tapas/
スワディヤーヤ(自己学習・聖典の学び)☜ 今日の記事
イーシュワラ・プラニダーナ(信愛・神への委ね)