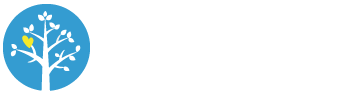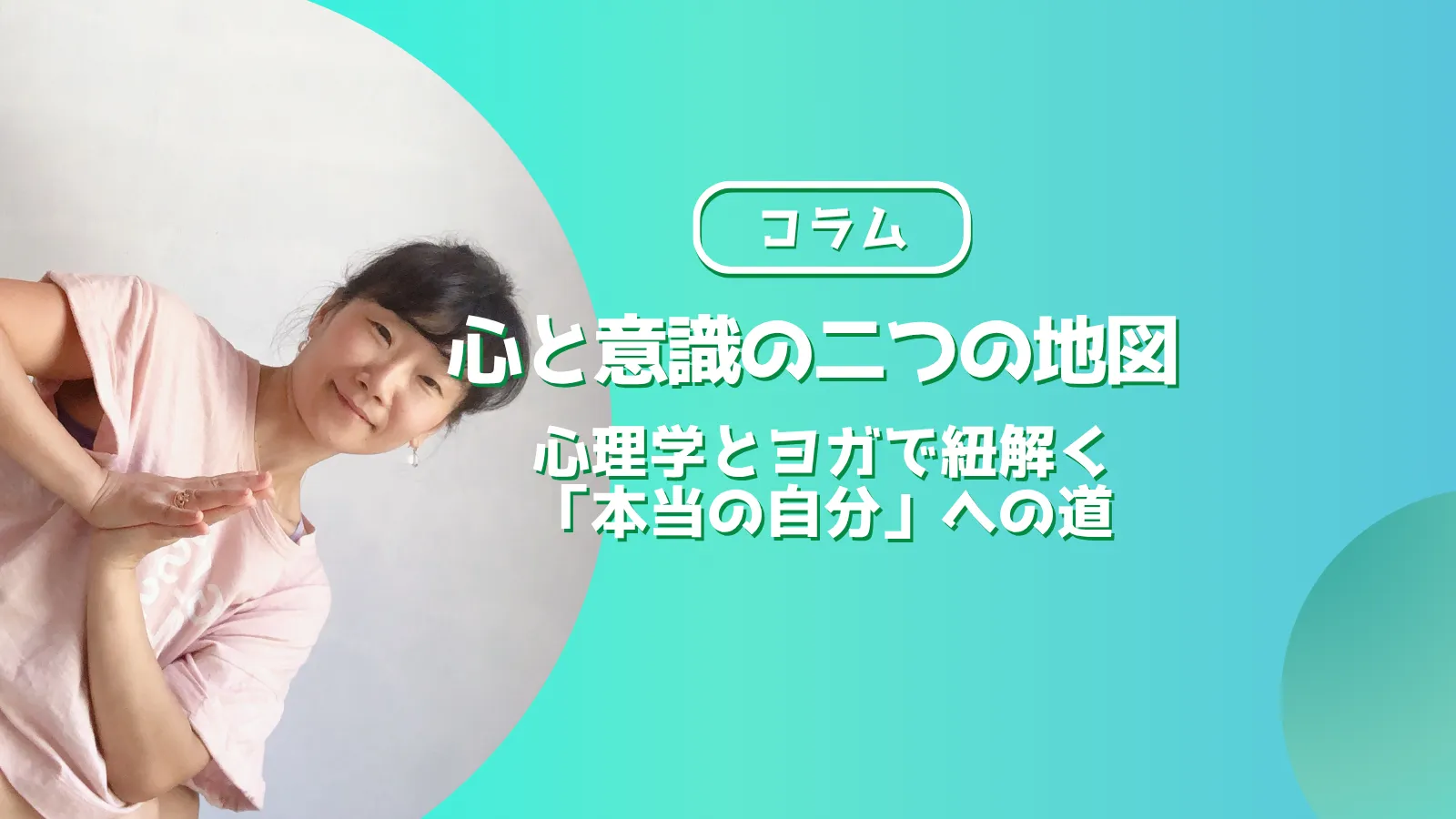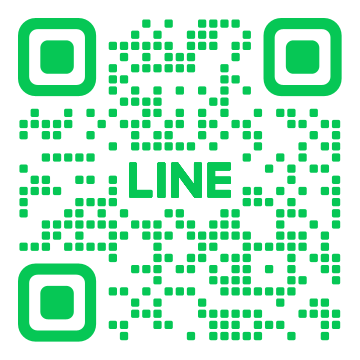漠然とした不安、人間関係の悩み、本当の自分って何だろう?
現代を生きる私たちの抱えている問題はそのほとんどが、心に関することなのではないでしょうか。
その答えを探す時、私たちは何を頼りにすれば良いのでしょうか。
心理学、哲学、スピリチュアル、そしてヨガ。
どれも人間の内なる世界(心)を探るために生まれた叡智です。
ここ最近では、「潜在意識」「無意識」「セルフ」「トラウマ」など、心理学の言葉で“心”を語ることが当たり前になっています。一方、ヨガ哲学の中には「マナス」「アハンカーラ」「ブッディ」「チッタ」といった、古代インドから受け継がれてきた“心の構造”があります。
どちらも人間の意識(心)を深く理解しようとしてきた体系ですが、焦点を当てている方向が少し違います。
この記事では、心理学とヨガの言葉の対応関係を通して、「心とは何か」「意識とは何か」をもう一度見つめ直し、あなたの「本当の自分」への道を探るヒントを見つけていきましょう。
心理学でみる心とヨガ哲学でみる心の違い
“深さ”で見る意識の層──心理学の地図
心理学では、意識をまるで深い井戸のように「深さ」でとらえます。
もっとも表層にあるのが、今この瞬間、あなたがこの文章を読んだり、コーヒーを飲んだりしている日常的な意識(健在意識)。その下には、普段は意識されていない無意識(潜在意識)が広がり、さらに奥には人類共通の深い層、集合的無意識があります。
| 意識の層 | 内容 | 主な機能 | 具体例 | |
|---|---|---|---|---|
| 顕在意識 | 今ここで思考・判断している意識 | 感情・言語・選択・行動 | 今日何を着るか決める、友達と会話する、ブログを読む | |
| 潜在意識 | 個人的無意識 | 抑圧された記憶や感情 | 習慣・記憶・コンプレックス | 過去の失敗が、なぜか何度も頭をよぎる経験 |
| 集合的無意識 | 人類共通の原型的イメージ(ユング心理学) | 本能・象徴・夢の世界 | 英雄の物語に心惹かれる、大自然に畏敬の念を抱く | |
| 超意識 | 個を超えた霊的意識(トランスパーソナル心理学) | 直観・創造性・ワンネス体験 | ふとした瞬間のひらめき、瞑想中の深い安らぎ | |
心理学では、心を“縦に掘る”ようにして、見えない深層に潜むパターンを理解していきます。私たちの行動や感情の裏に隠された、無意識の要因を探るアプローチと言えるでしょう。
“働き”で見る意識の構造──ヨガの地図
一方ヨガ哲学では、意識を“機能”で見ます。
それぞれの心的器官がどのように働いているかに注目し、心を分解して観察するアプローチです。
| 心の構造 | サンスクリット語 | 機能 | 対応する心理学的層 |
|---|---|---|---|
| 感覚心 | マナス (Manas) | 五感を通して感じ、考える。反応を生む。 | 健在意識 |
| 自我意識 | アハンカーラ (Ahaṃkāra) | 「私」「私の」と認識し、分離を生む。 | 個人的無意識 |
| 智性・直観 | ブッディ (Buddhi) | 識別・洞察・直観的理解。 | 超意識 |
| 心の総体 | チッタ (Citta) | 上の3つすべてを含む“心の場”。意識全体のフィールド | (心理学の意識全体に対応) |
| 観照者 | プルシャ (Purusha) | 心を見ている“変わらない意識”。 | 心理学には直接対応なし(Selfに近い) |
ヨガは、心の深さよりも「どの働きがどの方向に動いているか」を観察します。
美味しいものを食べた時に「美味しい!」と感じるのがマナス、「これは“私が”食べるべきものだ」と“私”を主として認識するのがアハンカーラ、「これは体に良いものか」と判断するのがブッディ、といった具合に、心を機能的にとらえるのです。
そして、特に、心(意識)そのものを見つめる「プルシャ(純粋意識)」という概念は、心理学には直接的な対応がなく、ヨガ哲学の大きな特徴の一つです。
二つの地図の違い──「掘る」か「観る」か
心理学とヨガ哲学は、どちらも人間の心を探求する道ですが、アプローチの方向性がまったく異なります。
- 心理学は「下から上へ」:無意識から意識化へ。
- ヨガは「上から下へ」:意識(超意識)から心の場へ。
🪶 心理学の方向──下から上へ(無意識から意識へ)
心理学は、心の深層へ潜っていく“下降の旅”のように始まり、そこから“上昇”して意識化していく道です。
無意識に抑圧された感情や記憶、影(シャドウ)を掘り起こし、それを言葉にして、光を当てていく。いわば、心の地下室にランプを持って降りていくような作業です。見えない部分を明るみに出すことで、人は再び自分を取り戻し、癒しや統合、深い自己理解へと向かいます。このプロセスは、まさに“上昇の心理学”と言えるでしょう。
🌞 ヨガの方向──上から下へ(意識から心へ)
一方のヨガは、出発点がまったく逆です。
「意識」そのもの──つまり“光”の側から始まります。プルシャ(純粋意識)はすでに光り輝いており、心(チッタ)はその光を映す“湖面”のような存在。その湖面が波立っていると、光は歪み、世界も乱れて見えます。
ヨガの実践は、まずこの心の波を静めることによって、もともとの光をそのまま映し出そうとします。つまり、意識の高みから、心へと光を降ろすアプローチなのです。静寂を通して、心の状態を「観る」ことに重きを置きます。
🌿 二つの道の比較
心理学は心の奥底を探索し、問題を解決することで上に昇っていく。ヨガは心の純粋な源から始まり、その光で心全体を照らし出す。どちらのアプローチにも優劣がついているわけではなく、どちらも私たちをより豊かな意識へと導いてくれる大切な道なのです。
カオン式「在り方としてのヨガ」の場合──“上昇”と“下降”の架け橋
人の心は、どちらか一方向からだけでは真に整いません。いえ、正確な表現をすれば整いにくいかなと思います。
心理学が「下から上へ」と無意識から意識への上昇を促し、ヨガが「上から下へ」と意識の光を心と体へ降ろすように、カオン式の在り方としてのヨガでは、この二つの流れを往復して統合させていくように働きかけています。
感じる(心理的な体験) → 気づく(ヨガ的な観照) → 分かる(識別と理解) → 在る(静寂と充足)
感情を感じ切ることで“心の下層”が解け、そこに意識の光を注ぐことで“上層”が澄んでいく。この双方向の働きこそが、現代に生きる人々にとっての「実際に使えるヨガ哲学」を形づくっています。カオン式「在り方としてのヨガ」を通して、あなたは日々の小さなストレスに囚われず、感情の波に飲まれることなく、しなやかに生きる力が育まれていくことを実感できるでしょう。
現代にマッチした「在り方としてのヨガ」
カオン式在り方としてのヨガは、心理療法のように感情を分析することを目的とはしていません。また、古典ヨガのように修行的な禁欲を求めるものでもありません。
体を通して感じ
その感じを意識へ昇華させ
再び日常へと還す
このプロセスは、現代の生活を送る私たちのリアルな場──仕事・家庭・人間関係・社会の中で自然に実践できるよう構成されています。心理学のように“心を掘る”だけでもなく、ヨガ哲学のように“心を超える”だけでもない。感じることを通して心を整え、意識を深める道。それが「在り方としてのヨガ」です。
まとめ──二つの流れが出会う場所に生まれるもの
心理学の上昇は“癒し”をもたらし、ヨガの下降は“静けさ”をもたらします。
カオン式の在り方としてのヨガは、この二つの流れが出会う“中間点”──つまり「今ここ」に立ちます。
上からも、下からも。
心理と意識、感情と静寂。
その両方を活かして生きるのが、現代のヨガだと思っています。そしてそれは、古典でもスピリチュアルでもなく、現代人の現実に根ざした、体験としてのヨガ哲学なのではないでしょうか。
この二つの流れを自然に組み合わせて生まれた『カオン式在り方としてのヨガ』は、心と意識の両方に橋を架けた“新しいヨガの形”だと感じています。現代の普通の生活を送る人が、無理なく、でも確実に“本来の自分”に還っていける。それこそが、私が「在り方としてのヨガ」で伝えたいことです。
そして、それが体現されている時、人は生きることそのものがアート(作品)になるのだと思います。